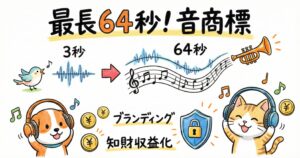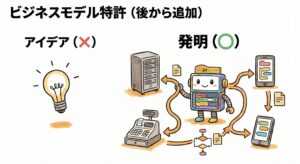訂正審判を駆使した特許権の戦略的防衛と収益力強化:プロフェッショナルが知るべき実務の核心

1. はじめに:特許権の真価を問う「訂正」の戦略的意義
株式会社IPリッチのライセンス担当です。
本記事では、特許実務において極めて専門性が高く、かつ企業の知財戦略の成否を分ける重要な手続きである「訂正審判」について解説します。特許は一度登録されれば絶対的な権利として安泰というわけではありません。競合他社からの無効審判請求や、侵害訴訟における無効の抗弁など、事後的な攻撃に晒されるリスクは常に存在します。こうした局面において、特許権者が自らの権利を守り抜き、かつ事業活動やライセンス活動との整合性を保つために許された唯一の手段が「訂正」です。
訂正審判は、単なる明細書の誤記訂正手続きではありません。それは、無効理由を巧みに回避しながら権利範囲を維持し、時には係争における勝敗を逆転させるための「高度な防衛戦術」です。本稿では、訂正審判の制度趣旨や法的要件といった基礎知識から、侵害訴訟における具体的な活用戦略、さらには「実質的変更」の境界線をめぐる判断基準まで、プロフェッショナルな視点から網羅的に論じます。また、これらの戦略的運用がいかにして「知財の収益化」に貢献するかについても言及します。本記事が、皆様の保有する特許資産の価値を最大化し、強固なポートフォリオを構築するための一助となれば幸いです。
2. 特許収益化とプラットフォーム活用の重要性
特許権の維持・管理には多大なコストがかかりますが、その一方で、自社事業で活用されていない「休眠特許」が多くの企業の資産として眠ったままになっています。これらの特許は、適切な市場に流通させることで、新たな収益源へと転換できる可能性を秘めています。特許の価値は、保有しているだけでは顕在化しません。ライセンスや売買を通じて第三者に活用されて初めて、その経済的価値が実現するのです。
現在、特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」では、特許の無料登録を受け付けています。このプラットフォームは、特許を売りたい・貸したい企業と、技術を導入したい企業を効率的にマッチングさせる場を提供しています。保有特許の棚卸しを行い、収益化の可能性がある特許を市場に公開することは、知財経営の観点からも極めて有効な戦略です。コストセンターとなっている特許を、利益を生むプロフィットセンターへと変革させる第一歩として、ぜひご活用ください。

3. 訂正審判の法的定義と審査基準における位置づけ
訂正審判とは、特許権の設定登録後に、特許明細書、特許請求の範囲、または図面の記載内容を特許権者自らが修正するために、特許庁に対して請求する審判手続きです。この手続きは特許法第126条に規定されており、特許付与後の瑕疵(欠陥)を治癒し、権利の無効を防ぐための重要な手段として機能します。
権利付与後の補正としての性質
特許出願の審査段階においては、審査官からの拒絶理由通知に対応して「補正」を行うことが認められています。補正は比較的柔軟に行うことが可能ですが、訂正審判は権利発生後の手続きであるため、その運用ははるかに厳格です。なぜなら、一度確定した権利範囲(特許請求の範囲)を安易に変更することを認めれば、その特許公報を信じて事業活動を行っていた第三者に不測の損害を与える恐れがあるからです。したがって、訂正審判は「公益的要請」と「特許権者の保護」のバランスの上に成り立っており、訂正が認められる範囲は法律で厳しく制限されています。
補正却下決定不服審判との相違
実務上、混同を避けるべき手続きとして「補正却下決定不服審判」があります。これは、審査段階において審査官がした補正却下の決定に対して不服がある場合に請求するものであり、権利化前の手続きです。一方、訂正審判は権利化後の手続きであり、その目的はあくまで既存の権利の維持・適正化にあります。この違いを明確に理解しておくことは、各フェーズにおける適切な対抗手段を選択する上で不可欠です。
4. 訂正が認められる厳格な要件と減縮の論理
訂正審判において訂正が認められるためには、以下の3つの目的のいずれかに該当しなければなりません(特許法第126条第1項)。これらは限定列挙であり、単に表現を改善したいといった理由での訂正は認められません。
特許請求の範囲の減縮
最も頻繁に利用され、かつ戦略的な重要性が高いのが「特許請求の範囲の減縮」です。これは、特許権の範囲をより狭く限定することを指します。例えば、無効審判において先行技術文献(引用文献)が提示され、その文献に記載された技術が自社の特許請求の範囲に含まれてしまっている場合、特許は「新規性」または「進歩性」を欠くとして無効となります。
このような事態を防ぐために、特許権者は特許請求の範囲に新たな構成要件を追加(限定)し、先行技術を除外するような形に権利範囲を「減縮」します。これにより、特許の有効性を維持しつつ、相手方の製品(イ号物件)が依然としてその減縮された範囲に含まれるようにコントロールすることが、知財担当者の腕の見せ所となります。
誤記または誤訳の訂正
明細書等の記載における明らかな誤りを訂正する場合です。「誤記」とは、その記載が誤りであることが明細書の記載自体から明らかであり、かつ正しい意味も文脈から自明である場合に限られます。また、外国語書面出願における翻訳の誤りを訂正する場合もこれに含まれます。
不明瞭な記載の釈明
特許請求の範囲や明細書の記載が不明確であり、技術的範囲が特定できない場合などに、その意味を明確にするための訂正です。これは、無効理由の一つである「記載要件違反(不明確)」を解消するために用いられます。
5. 実質的変更の禁止と判例に見る技術的範囲の解釈
訂正審判において最も高いハードルとなるのが「実質的変更の禁止」です。特許法第126条第6項は、訂正が「特許請求の範囲を実質的に変更するものであってはならない」と規定しています。
実質的変更の判断基準
「実質的変更」とは、訂正前の特許請求の範囲に含まれていなかった技術的思想を新たに追加したり、訂正前の範囲とは異なる対象に権利を及ぼすような変更を指します。たとえ形式的には「減縮」の要件を満たしているように見えても、その訂正によって第三者が予期せぬ不利益を被る場合は、実質的変更とみなされ却下されます。
例えば、構成要件の一部を削除したり、全く別の技術的要素に置換したりする行為は、通常、実質的変更に該当します。また、数値範囲を変更する場合でも、その変更によって技術的意義が一変してしまうような場合は認められません。
図面に基づく訂正とサポート要件の事例
訂正における「新規事項の追加禁止」と「実質的変更」の境界線については、各国の判例でも頻繁に争点となります。例えば、韓国の大法院(最高裁に相当)の判例では、特許明細書の本文には具体的な説明がなく、図面にのみ記載されていた技術的特徴を、登録後に特許請求の範囲に追加する訂正の可否が争われました。
この事案において裁判所は、明細書と図面全体から把握される実質的な内容を対比し、その訂正によって「発明の目的や効果」が変わらず、かつ第三者に不測の損害を与える恐れがないと判断し、訂正を認めました。この事例は、形式的な記載の有無だけでなく、発明の技術的本質(Technical Spirit)と、明細書全体からの「自明性」がいかに重要視されるかを示唆しています。日本の実務においても、訂正が「当初明細書等に記載した事項の範囲内」であるか否かは厳格に審査されますが、図面のみに記載された事項であっても、当業者がそこから技術的構成を明確に読み取れる場合には、訂正の根拠となり得る可能性があります。
6. 侵害訴訟における訂正審判の戦略的運用とタイミング
特許権侵害訴訟において、訂正審判は「盾」として機能します。特許法第104条の3は、特許に無効理由が存在することが明らかである場合、特許権者は権利を行使できないと定めています(権利濫用の抗弁)。これに対し、特許権者は訂正審判(または訂正請求)を行い、「訂正によって無効理由は解消されるため、権利行使は有効である」と再抗弁(Counter-Defense)を行うことができます。
訂正の再抗弁と審理の迅速化
かつては、侵害訴訟中に訂正審判が請求されると、裁判所は特許庁の審決が出るまで訴訟手続きを中止することが多く、解決が長期化する要因となっていました(いわゆるキャッチボール現象)。しかし、近年の実務では、審理の迅速化を図るため、裁判所が訂正の成立性(訂正が認められる蓋然性)を自ら判断し、特許庁の審決を待たずに判決を下す傾向が強まっています。
したがって、特許権者は侵害訴訟において無効の抗弁を受けた際、ただちに訂正審判を請求するだけでなく、その訂正が確実に認められるものであること、そして訂正後の権利範囲でも被告製品が侵害を構成することを、裁判所に対して迅速かつ説得的に主張する必要があります。
手続きの選択と90日ルール
侵害訴訟が提起された後に、特許権者が取り得る訂正手段には制限があります。特許法第126条第2項により、特許権侵害訴訟の提起後など特定の期間内(基本的には訴状送達等から90日以内等)であれば、無効審判が請求されていなくても訂正審判を請求できる場合があります。
一方で、相手方が特許庁に対して「特許無効審判」を請求してきた場合は、その手続き内において「訂正の請求」(特許法第134条の2)を行うことが原則となります。この場合、独立した訂正審判を請求することはできず、既に請求していた訂正審判も無効審判に係属する形になります。
韓国の事例では、侵害訴訟の事実審の弁論終結前に訂正を認める審決が確定するように訴訟指揮を進めることの重要性が説かれています。これは日本においても同様であり、訂正のタイミングを逸すると、最悪の場合、無効理由を抱えたまま判決が下され、敗訴するリスクがあります。プロフェッショナルには、相手方の無効主張の内容を先読みし、予め訂正案(予備的請求項)を準備しておく周到さが求められます。
7. 知財の収益化と訂正による資産価値の向上
最後に、訂正審判という手続きが「知財の収益化」にどのように貢献するかについて触れます。特許の価値評価において、最も懸念されるリスクは「無効化される可能性(Validity Risk)」です。
ライセンス交渉や特許売買(M&A含む)のデューデリジェンスにおいて、買い手やライセンシー候補は必ず特許の有効性を精査します。この際、広すぎる権利範囲や、公知技術を含んでしまっている瑕疵が見つかれば、特許の価値は著しく減損し、交渉は決裂するか、買収価格が大幅に叩かれることになります。
ここで、訂正審判を能動的に活用する意義が生まれます。特許権者は、交渉前に自ら先行技術調査を行い、潜在的な無効理由を発見した場合には、訂正審判によって予防的に権利範囲を適正化しておくことができます。瑕疵を取り除き、かつ自社製品やターゲット製品をカバーする「筋肉質で強固な特許」に磨き上げることで、法的安定性が高まり、相手方に対する交渉力は格段に向上します。
「守りの手続き」と思われがちな訂正審判ですが、その本質は特許という資産の品質管理であり、収益最大化のための「攻めのメンテナンス」といえます。我々知財専門家は、単に権利を維持するだけでなく、ビジネスにおけるキャッシュフロー創出を見据えた戦略的な訂正実務を推奨しています。
(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
特許庁, “補正却下決定不服審判(意匠、商標、平成5年12月31日以前の旧特許・旧実用新案出願)”, https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-sample_bill_sinpan.html
ジェトロ(日本貿易振興機構), “図面に基づいて登録特許の請求の範囲に技術構成を追加する訂正が請求の範囲の実質的変更ではないと判断した事例”, https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2017/case184_01.html
ジェトロ(日本貿易振興機構), “特許審判院において無効審決が下されると、特許権者(A社)は特許法院にその審決取消訴訟を提起し、それと同時に特許審判院に追加の技術構成を導入する訂正審判…を請求した”, https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2021/_467270.html
日本知的財産協会, “特許権侵害訴訟における訂正手続と審理遅延に関する考察”, http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2008_11_1471.pdf