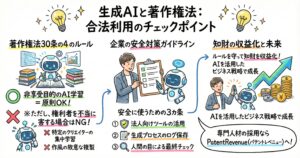プロフェッショナルが知るべき特許権存続期間の延長制度:最新の最高裁判例が実務に与えた影響と「権利の効力範囲」の詳細解説
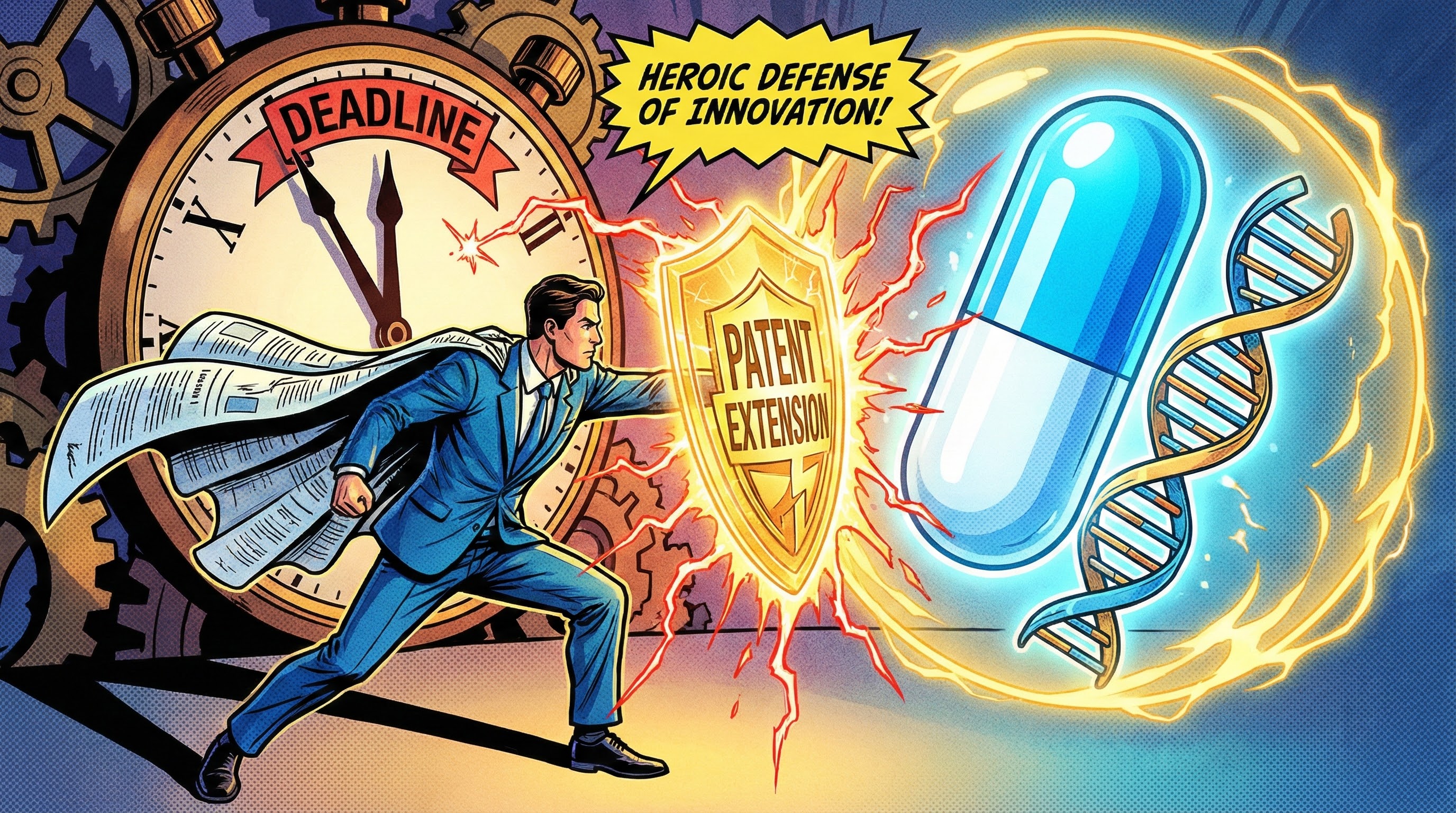
はじめに:知財戦略の要諦となる延長制度の理解
株式会社IPリッチのライセンス担当です。
医薬品や農薬など、研究開発に長期間を要する分野において、特許権の存続期間延長制度は事業の収益性を左右する極めて重要な要素です。本記事では、製薬・バイオ・化学メーカーの知財担当者や経営層、弁理士等の専門家に向けて、特許法第67条に基づく延長登録制度の核心を解説します。特に、実務に革命的変化をもたらした「パシーフ事件」「アバスチン事件」の両最高裁判決が示した判断基準(実質的同一性の解釈)と、それを受けた2020年の審査基準改定のポイント、さらには中国など最新の海外動向までを網羅的に分析します。最後に、これらの制度を駆使した「知財の収益化」戦略についても言及します。複雑化する延長実務を正しく理解し、貴社の知財ポートフォリオの価値最大化にお役立てください。
特許資産の価値最大化と「PatentRevenue」の活用
特許制度は、発明を公開する代償として一定期間の独占権を付与するものですが、その真価は「権利行使」や「自社実施」だけにとどまりません。企業の競争力の源泉である特許も、活用されなければコストを生むだけの負債となりかねません。特に、主力事業以外の技術や、開発が中断したプロジェクトに関連する休眠特許は、他社にとっては事業化の鍵となる貴重な経営資源である可能性があります。
もし、貴社に収益化を図りたい特許や、活用先を模索している技術がございましたら、ぜひ特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」への登録をご検討ください。PatentRevenueは、技術を売りたい企業と買いたい企業をダイレクトに繋ぐプラットフォームであり、特許の登録は無料で行えます。「見えざる資産」を市場価値のある「収益資産」へと転換する第一歩として、https://patent-revenue.iprich.jp より是非ご登録ください。
特許法における「存続期間の延長登録制度」の基本的枠組みと要件
1. 制度の趣旨と法的根拠
特許権の存続期間は、原則として出願日から20年で終了します(特許法第67条第1項)。しかし、医薬品や農薬等の分野では、安全性確保のための法規制(薬機法や農薬取締法)に基づく承認・登録(以下「処分」)を受ける必要があり、その審査・試験期間中は特許発明を実施(製造販売)することができません。この「浸食された期間」を回復し、投下資本の回収機会を保障するために設けられたのが、存続期間の延長登録制度です。
2. 延長登録の要件と「政令で定める処分」
延長が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 処分の必要性: その特許発明の実施に、政令で定める処分(医薬品の製造販売承認、農薬の登録等)を受けることが必要であったこと。
- 期間の算定: 延長期間は、処分を受けるために実施できなかった期間(最大5年)です。
- 出願のタイミング: 処分を受けた日(承認日)から3ヶ月以内、かつ本来の存続期間満了の6ヶ月前までに延長登録出願を行う必要があります。
実務上、最も争点となるのは「その処分を受けることが必要であったか(特許法第67条の3第1項第1号)」という点です。特に、先行する医薬品(先行処分)が存在する場合に、後続の医薬品(本件処分)について延長が認められるかどうかが、長らく議論の的となってきました。
最高裁判決による実務の大転換:「パシーフ」から「アバスチン」へ
日本の延長登録実務は、2つの重要な最高裁判決によって、その判断基準が劇的に変更されました。これにより、製薬企業のライフサイクルマネジメント(LCM)戦略は大きな修正を迫られることとなりました。
1. パシーフ事件最高裁判決:技術的範囲と延長の可否
【事件の概要】 パシーフ事件(最判平成23年4月28日)は、DDS(ドラッグ・デリバリー・システム)製剤に関する特許の延長が争われた事案です。特許庁は、有効成分と効能・効果が同一の先行医薬品(先行処分)が存在することを理由に、後続の徐放性製剤(本件処分)についての延長登録を拒絶しました。
【判決の要旨と影響】 最高裁は特許庁の判断を覆し、以下の基準を示しました。 「先行処分の対象となった医薬品が、延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということはできない」。
つまり、先行医薬品が特許発明(この場合はDDS製剤の発明)の技術的範囲外であれば、たとえ有効成分が同じでも、その特許発明を実施するためには新たな処分が必要であったと認められることが確定しました。これは、製剤特許等の周辺特許による保護期間延長の道を拓く画期的な判決でした。
2. アバスチン事件最高裁判決:「実質的同一性」の審査基準
【事件の概要】 パシーフ判決後、さらに踏み込んだ判断が示されたのがアバスチン事件(最判平成27年11月17日)です。本件では、先行医薬品も後行医薬品も共に特許発明(成分特許)の技術的範囲に属していましたが、後行処分では「用法・用量」が変更されていました。特許庁は「成分特許の実施は先行処分で可能だった」として拒絶しました。
【判決の要旨と影響】 最高裁はここでも特許庁の処分を取り消し、「実質的同一性」という新たな判断枠組みを提示しました。 「先行処分と本件処分を比較し、特許発明の種類等に照らして医薬品としての実質的同一性に直接関わる審査事項(成分、分量、用法、用量、効能、効果)について両処分を比較した結果、先行処分の対象となった医薬品の製造販売が、本件処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められるとき」に限り拒絶すべきであるとしました。
この判決により、成分特許であっても、**「用法・用量」や「効能・効果」**が異なる承認を得た場合、それぞれについて特許期間の延長が認められる可能性(複数回延長)が明確になりました。これは、「1成分1延長」という従来の運用を根底から覆すものであり、適応拡大等の開発インセンティブを強力に後押しするものです。
2020年審査基準改定と実務上の留意点:実質的同一性の具体的判断
アバスチン判決を受け、特許庁は審査基準を改定し(2020年適用開始)、最高裁が示した「実質的同一性」の判断プロセスを明文化しました。
1. 改定審査基準のポイント
改定後の審査基準では、延長登録の拒絶理由(第67条の3第1項第1号)の判断において、先行処分と本件処分の「審査事項」を厳密に対比することが求められます。
- 比較項目: 医薬品の場合、「成分、分量、用法、用量、効能、効果」。
- 判断基準: これらに相違があれば、原則として「実質的同一」とはみなされず、延長が認められます。
2. 実務家が注意すべき「包含」の概念
ただし、無制限に延長が認められるわけではありません。先行処分の包含範囲(実質的同一の範囲)については、重複して延長を認めることはできません。例えば、先行処分で「広義の用法」が承認されており、本件処分がその一部を具体化したに過ぎない場合などは、「包含する」と判断され拒絶されるリスクがあります。 したがって、開発段階から承認申請における「用法・用量」や「効能・効果」の記載(ワーディング)を、先行薬と明確に区別できるよう戦略的に設計することが、特許延長を勝ち取るための重要な実務テクニックとなります。
グローバル知財戦略:中国・米国・欧州における延長制度の比較
日本企業がグローバル展開する際、各国の延長制度の差異を理解することは不可欠です。特に近年、制度整備が急速に進む中国の動向は注目に値します。
1. 中国における特許期間延長制度(PTE/PTA)の最新動向
中国では2021年の専利法改正により、特許期間の延長制度が導入され、2024年1月の実施細則施行により運用が本格化しました。
- 対象: 「新薬」に関連する特許。ただし、中国で「クラス1(革新的新薬)」または一部の「改良型新薬」として承認されたものに限られます。
- 制限: 延長期間は最大5年、上市後の総有効期間は14年が上限です。最も注意すべきは、**「1つの医薬品につき延長できる特許は1つのみ」かつ「1つの特許につき延長できる医薬品は1つのみ」**という制限です。 日本では1つの特許で複数の適応症(医薬品)について延長することや、1つの医薬品で物質・製法・用途の複数の特許を延長することが可能ですが、中国では「選択」が必須となります。どの特許(物質か用途か)で延長申請を行うかが、ジェネリック参入時期を決定づけるため、極めて高度な戦略的判断が求められます。
2. 米国・欧州との比較
- 米国(Hatch-Waxman法): 1つの承認につき延長できる特許は1つのみ。日本と異なり「医療機器」も対象に含まれます。
- 欧州(SPC制度): 特許期間満了後に最大5年間の保護期間を追加する形式。小児用医薬品開発に対する延長(+6ヶ月)などのインセンティブが充実しています。
知財の収益化に向けた戦略的ポートフォリオ・マネジメント
延長特許による「パテントクリフ」回避と収益維持
特許期間の延長は、主力製品の独占期間を延ばし、「パテントクリフ(特許切れによる売上急減)」を先送りするための最強の防衛策です。しかし、単に物質特許を延長するだけでなく、アバスチン判決で認められた「用法・用量」や「製剤」の変更に伴う周辺特許の延長を組み合わせることで、特許網(パテント・ポートフォリオ)を重層的に強化することが可能です。 延長された特許権は、ジェネリック医薬品の参入を阻止する防波堤となるだけでなく、バイオシミラーメーカー等に対する有利な条件でのライセンス交渉(クロスライセンスや和解金)の材料としても機能します。
結論:「見えざる資産」の積極的な収益化へ
本記事で解説した特許期間延長制度は、自社事業を守るための「守り」の戦略であると同時に、特許の経済的価値を最大化する「攻め」の基盤でもあります。延長によって残存期間が長くなった特許は、ライセンス市場において極めて高い評価額がつきます。 自社で開発を継続しない特許であっても、延長登録の可能性があるもの、あるいは特定の用法・用量において権利行使が可能なものは、他社にとって喉から手が出るほど欲しい資産かもしれません。 知財専門家の皆様には、延長制度を駆使して権利の「質」と「期間」を最大化し、それを自社実施のみならず、ライセンスアウトや売却といった「知財の収益化」へと繋げる多角的な出口戦略を描くことが求められています。
(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献リスト
- 経済産業省『特許法等の一部を改正する法律案(特許権の存続期間の延長制度の見直し)』関連資料
- 特許庁『特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について』(令和2年3月)
- 最高裁判所第二小法廷判決 平成23年4月28日(平成21年(行ヒ)第326号)「パシーフカプセル事件」
- 最高裁判所第三小法廷判決 平成27年11月17日(平成26年(行ヒ)第356号)「アバスチン事件」
- 日本弁理士会『Q&A 特許権存続期間の延長登録制度』
- JETRO『中国における特許権存続期間の延長制度の概要』(2021年・2024年更新情報)