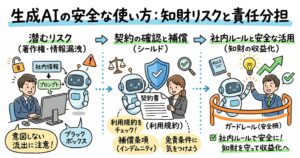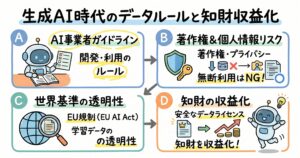ビジネスモデル特許の可能性と限界 – サービス業における知財保護の実情

株式会社IPリッチのライセンス担当です。
ビジネスモデル特許の可能性と限界、つまりサービス業におけるビジネスモデルをどのように知的財産として保護できるのか、その現状と課題について解説します。本記事では、ビジネスモデル特許の基本から国内外の動向、活用事例、そして制度上の制約までを包括的に述べます。
ビジネスモデル特許とは
ビジネスモデル特許とは、ビジネス上の方法や仕組みを特許として保護したものを指します。典型的にはIT技術を用いて実現されるビジネス手法(いわゆるビジネス方法発明)がその対象です。日本の特許庁ではこの種の発明を「ビジネス関連発明」と呼び、国際特許分類IPCで G06Q(電子商取引や業務処理など)に分類される出願を指標としています【1】。重要なのは、単なるアイデアや経営手法そのものは特許にならない点です。特許法上、「発明」とは自然法則を利用した技術的なアイデアでなければなりません【2】。したがって、斬新なサービスのアイデアであっても技術(テクノロジー)と結びついていない場合には特許の保護対象になりません【1】。例えば「新しい契約形態」や「人のオペレーション手順」自体は技術とはみなされず、このままでは特許出願しても「単なる業務上の取り決めに過ぎず技術的思想ではない」として拒絶されてしまうリスクがあります【2】。
しかし裏を返せば、IT技術を活用して実現されたビジネスモデルであれば特許として認められる可能性があります【1】。言い換えると、ビジネスモデル特許を成立させるには、そのビジネスの新規性や有用性を具体的な技術手段によって支える必要があります。実務上は、コンピュータシステムやソフトウェアを活用した発明としてビジネスモデルを表現し直す方法がよく採られます【2】。例えば、新サービスの特徴が「顧客と企業の契約内容」にある場合、単に契約条項を記述するのではなく、「サーバやユーザー端末がどのようにデータ処理を行い契約を実現するか」という形で記載します【2】。また、人間の判断や操作が中心となる業務フローの場合でも、そのプロセスを支援・自動化するソフトウェアの動作として定義し直すことで、技術的な発明として特許要件を満たすよう工夫します【2】。このように技術面へ落とし込むことで初めて、ビジネスモデルが「発明」として特許庁に認められる土俵に立つわけです。
要約すれば、ビジネスモデル特許とは「ビジネス方法 × ICT」による発明です【1】。サービス業を含む様々な分野でIT技術を組み合わせたビジネスの革新が進む中、そのような技術起点のビジネスモデルは特許による保護が可能となっています。一方で、技術を伴わない純粋なビジネス上のアイデアは依然として特許にならないため、その線引きが実務上のポイントになります。
サービス業におけるビジネスモデル特許の動向
かつて特許は製造業の発明(モノづくりの技術)を保護する制度という色彩が強く、サービス業のビジネスモデルは保護が難しいとされてきました。しかし1990年代末から2000年代初頭にかけて、米国でのビジネス方法特許ブーム(金融取引手法の特許化やAmazonのワンクリック特許など)が起爆剤となり、日本でも「ビジネスモデル特許」が注目されるようになりました。2000年前後には関連特許の出願が急増し一種のブームとなりましたが、その後一旦減少した経緯があります【1】。当時はまだ審査基準も手探りで、特許として認められる範囲が定まっていなかったことも影響したと考えられます。
しかし近年、状況は大きく変化しています。サービス産業を含む社会全体のデジタル化・ソフトウェア化が進み、「モノからコトへ」と呼ばれる産業構造の転換の中で、サービス分野の技術革新に対する特許出願が再び増加傾向にあります【1】。特許庁の調査によれば、日本におけるビジネス関連発明(ビジネスモデル特許)の出願件数は2010年代前半に低迷した後、2012年頃から増加に転じ、2018年以降は年間1万件を超える水準で推移しています【1】。この背景には、企業がソリューション志向で研究開発を行うようになったことや、スマートフォン・SNSの普及、AIやIoTの進展によってICTを活用した新たなサービス分野(フィンテック等)が拡大していることが挙げられます【1】。実際、特許庁データでも近年は金融サービス(スマホ決済やフィンテック)の分野が顕著な伸びを示しています【1】。
サービス業に関連するビジネスモデル特許出願も年々増え、その中心分野が明らかになっています。特許庁の分類では、以下のような領域で出願が多くなっています【1】:
- サービス業一般(宿泊、飲食、運輸、通信、不動産等のサービス全般):ICTを組み合わせたサービス提供モデルの特許出願が最も多い領域です。例として、宿泊予約システムや配車サービスなど、新しいサービス提供プラットフォームの発明が該当します。
- 電子商取引・マーケティング(ECサイト、フリマアプリ、ネット広告、マーケット予測など):オンラインで商取引やマーケティングを行うビジネスモデルの特許が活発です。フリマアプリやネットオークションの隆盛に伴い、この分野の出願も増加しています【1】。
- 業務管理・経営支援(社内業務システム、在庫管理、人員配置、プロジェクト管理など):企業内外の業務効率化や最適化に関する発明も増えています。特にAIを用いて在庫管理やスケジューリングを高度化するような発明が代表例です【1】。
- 金融・決済(ネットバンキング、電子決済、保険商品設計など):上記サービス業一般等に次いで出願件数が大きいのが金融分野です。スマートフォンを介した個人向け金融サービス(決済、投資アプリ等)の普及に伴い、この分野の特許出願が増えています【1】。
このようにサービス産業各分野でビジネスモデル特許の取得が進んでおり、サービス業のビジネスモデルも知財として積極的に保護・活用される時代になってきています。また、かつては低かったビジネス関連発明の特許査定率(特許が認められる割合)も近年では他の技術分野と同程度の70%台に達しており【1】、審査基準の明確化などにより特許が成立しやすくなってきている傾向が見られます。
サービス業におけるビジネスモデル特許の動向(海外)
サービス業の知財戦略を考える上で、日本だけでなく海外におけるビジネスモデル特許の扱いも押さえておく必要があります。各国で特許制度の運用が異なるため、グローバルに事業展開するサービス企業はそれぞれの状況に対応した戦略を取ることが重要です。
- 米国:ビジネスモデル特許の議論が最も早くから盛んなのは米国です。1998年の米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)によるState Street Bank判決以来、純粋なビジネス方法も特許の対象になり得るとの解釈が広がり、インターネット黎明期には大手企業からスタートアップまで多数のビジネス方法特許が成立しました。代表例としてAmazonの「ワンクリック注文」特許などが知られ、サービス分野でも特許取得が相次ぎました。しかしその後、抽象的なアイデアの特許適格性が問題視され、2014年の米最高裁 Alice 判決以降はソフトウェア・ビジネス方法分野の特許要件が厳格化されています。これにより一時はビジネス関連特許の成立件数が落ち込みましたが、2019年にUSPTO(米国特許商標庁)が審査指針を改訂して基準を明確化したことで、近年は年間約2万件前後で推移しています【1】。米国では依然としてソフトウェアを用いたビジネスモデルの特許が数多く成立していますが、純粋な商慣行にとどまる出願は特許にならない点に注意が必要です。
- 欧州:欧州特許庁(EPO)はビジネス方法の特許保護に慎重な姿勢で知られます。欧州特許条約では「知的活動の計画・方法や商業上の方法」はそのままでは特許の対象から除外されると規定されており、技術的貢献が認められないビジネスモデル発明は特許になりません。コンピュータ実装された発明であっても、単なるビジネス上のルールや計算方法をコンピュータにやらせただけでは進歩性(発明の非容易性)なしと判断される傾向が強いです【1】。そのため欧州へのビジネスモデル関連の特許出願件数は主要国の中でも最も少ない水準に留まっています【1】。サービス業企業にとっては、欧州では同じ発明でも特許取得が難しい場合があることを念頭に置く必要があります。
- 中国:中国では近年ビジネス関連発明の特許出願が爆発的に増加しています。フィンテックや電子商取引の隆盛に伴い、中国企業や外資企業が中国特許を積極的に取得しており、その件数は年数万件規模と米国・日本を大きく上回っています【1】。中国の特許制度でも抽象的アイデアは特許不可ですが、AIや電子商取引を含むソフトウェア発明全般に比較的寛容な審査傾向が指摘されます。サービス業の巨大市場を背景に、中国ではビジネスモデル特許が競争力強化の重要な手段として位置付けられています。
以上のように、ビジネスモデル特許の国際的な扱いは一様でないのが現状です。自社のサービスモデルを海外展開する場合、米国では特許化できても欧州では難しい、といったケースもあります。また各国で判例や審査ガイドラインの変更が起きる可能性もあり、最新情報のフォローが重要です。サービス業における知財保護戦略では、狙いとする市場ごとに特許取得の可否を見極め、必要に応じて別の知財手段(例えば営業秘密や著作権による保護、あるいは速度優先のビジネス展開)も組み合わせる柔軟性が求められます。
ビジネスモデル特許の可能性とメリット
ビジネスモデル特許を取得することは、サービス企業にとってどのようなメリットがあるでしょうか。ここでは、その可能性についていくつかの観点から述べます。
1. 模倣防止と競争優位の確立: 他社が容易に真似できないユニークなビジネスモデルは、特許によって法的独占権を付与することで模倣を抑止できます。サービス業ではアイデアが知れ渡ると素早く追随されることが多いですが、特許権による保護は一定期間(出願から最長20年)競合他社を排除できる強力な武器になります。例えばフィンテック分野のスタートアップが画期的なサービス方式を特許化しておけば、大企業が同様のサービスに参入する際に躊躇させる効果を期待できます。その結果、自社サービスの競争優位を長く維持し、市場シェアやブランド力を高めることにつながります。
2. ビジネス提携や資金調達への追い風: 特許は単に権利保護するだけでなく、企業の信用力を高める無形資産でもあります。特にサービス業のスタートアップにとって、自社のビジネスモデルを特許出願・権利化していることは、技術力と独自性のアピール材料となります。実際の事例でも、ある新興企業が保有するビジネスモデル特許群が大企業との提携交渉の切り札になったケースがあります【3】。特許を取得しておくことで「自社の技術が他社特許を侵害していない」という裏付けにもなり、大企業から見て協業リスクが低いと評価される側面があります【3】。また、ベンチャーキャピタルなどからの資金調達においても、独自の特許を持つ企業は将来性が高いと判断されやすいと言われます。サービス分野では形のないビジネスモデルこそが企業の価値ですので、それを権利という形で担保することは投資家やパートナーへの大きな安心材料となります。
3. ライセンスによる収益化: 取得したビジネスモデル特許は自社で独占実施するだけでなく、ライセンス供与によって収益源とすることも可能です。他社が自社特許を実施したい場合に使用許諾契約を結べば、ライセンス料収入が得られます。特許は「攻め」のツールであると同時に適切に管理すれば「儲ける」手段にもなり得ます。実際、ビジネスモデル特許を積極的に活用してライセンス展開する企業も存在します。また、自社では手がけていないサービスモデルでも関連特許を取得しておき、後に業界全体にその手法が普及した際にライセンス収入を得る、といった戦略も考えられます。サービス産業では業態転換や事業提携が頻繁ですが、その中で特許権が取引材料となり、特許の売買・ライセンス市場で価値を発揮する可能性があります。特に昨今は特許売買やライセンス仲介のプラットフォームも登場しており(後述のPatentRevenueなど)、ビジネスモデル特許を資産として流動化する環境も整いつつあります。
4. 参入障壁の構築: 特許権を駆使して広範なクレーム(権利範囲)を確保できれば、業界における強力な参入障壁を築けます。例えばフィンテック領域のあるベンチャー企業は、自社のサービスに関連する特許を多数取得することで、大手企業による類似サービスの開発を思い留まらせ、むしろ大手側から協業を打診される状況を生み出しました【3】。このように、サービス業でも特許網を張り巡らせることで巨人に対抗する防護壁を構築できるのです【3】。参入障壁があれば自社が市場で成長する時間を稼ぐことができ、その間に顧客基盤やブランドを確立してしまう戦略も有効となります。
以上のように、ビジネスモデル特許には競争優位の維持・資産価値の向上・収益機会の拡大といった多くの可能性があります。サービス業の企業にとって、自社の独創的なビジネスモデルを適切に特許で囲い込むことは、攻守両面で事業戦略上有益と言えるでしょう。
ビジネスモデル特許の限界と課題
一方で、ビジネスモデル特許には固有の限界や注意点も存在します。制度上・運用上の課題を理解しておかないと、期待した効果が得られなかったり無用なリスクを抱えたりする恐れがあります。ここでは主な限界・デメリットを整理します。
1. 特許要件上のハードル: 前述の通り、ビジネスモデルそのものは技術ではないため、そのままでは特許になりません。特許として成立させるには技術的アイデアへ落とし込む必要があり、この要件(発明該当性)のハードルが第一に立ちはだかります【2】。無理に技術要件を満たすよう工夫しても、新規性・進歩性(従来になかった非自明な発明であること)の要件もクリアしなければなりません。ビジネスのアイデア自体が斬新でも、それを実現する技術手段が平凡であれば「既存の技術の寄せ集めに過ぎない」と判断される可能性があります。特に「コンピュータを使う」という点だけでは現代では当たり前になっており、それだけで進歩性を認めさせるのは困難です。結果として、特許出願しても審査で拒絶されるケースや、権利範囲が限定的になってしまうケースが少なくありません。ビジネスモデル特許の出願数に比して特許査定件数が長らく伸び悩んだのも、この要件上の難しさが一因でした【1】。
2. 権利行使の難しさ: 仮にビジネスモデル特許を取得できても、それを実際のビジネス上で行使(エンフォース)するのは難しい場合があります。サービス業のビジネスモデルは往々にして複数の主体やシステムが関与するため、特許請求の範囲内で他社の侵害行為を特定しにくいことがあります。例えばオンラインプラットフォームのビジネスモデル特許では、サービス提供者・ユーザー・第三者が相互作用するプロセス全体をカバーしますが、競合が一部だけ変更したサービスを提供すれば直接の侵害を構成しない可能性があります(いわゆるデザインアラウンドの余地が大きい)。また、サービスは目に見えにくく、侵害の発見や立証が困難な場合もあります。製品特許のように物の形で残るわけではなく、相手がサーバ上で何をしているかは外部から把握しづらいためです。このように権利を取ったはよいが使いこなせないリスクは覚悟する必要があります。
3. 時間と費用の問題: 特許取得には出願から権利化まで少なくとも1~2年以上の時間と、審査請求や代理人費用など相応のコストがかかります。サービス業のビジネスモデルは市場の変化が激しく、せっかく特許を取得した頃にはそのビジネス自体が陳腐化していた、という事態も起こり得ます。例えばITサービスでは数年で業態や技術が移り変わるため、特許取得のスピードとビジネス環境のギャップが課題となります。さらに海外展開するなら各国ごとに出願が必要で、費用は倍増します。欧州で特許が取れず他地域のみ取得という場合、グローバルには不完全な保護となります。このようにビジネスモデル特許は時間・コスト投資に見合うリターンが得られるか慎重に判断する必要があります。
4. 法的安定性の問題: ビジネスモデル特許を取り巻く法環境は比較的新しく、判例や制度変更によって将来状況が変わるリスクがあります。実際、米国では一度成立した多数のビジネス方法特許が裁判で無効化されたり、法改正により過去には無効主張すらできなかった先使用権(ビジネス方法特許に対する先行実施者の保護)が認められるようになったりと、状況がめまぐるしく変化しました。日本においても、ビジネス関連発明の審査基準は時代とともにアップデートされてきています。したがって、現時点で有効なビジネスモデル特許でも、将来的な法解釈の変化や他社からの無効審判請求などで権利が揺らぐ可能性があります。サービス企業は特許に過度に依存しないバランスが重要で、他の知財戦略や市場戦略と組み合わせてリスクヘッジをする必要があります。
5. 秘密保持とのトレードオフ: 特許出願は発明内容を世界中に公開する行為でもあります。サービス業のノウハウの中には、公表せず秘密として運用した方が優位性を保てる場合もあります(いわゆる営業秘密による保護)。特許を取ると競合他社はその内容を詳細に知ることができ、仮に特許で直接保護されない部分についてはヒントを与えてしまう可能性があります。例えばアルゴリズムや顧客データの活用法など、特許請求の範囲に入らなかった要素まで明らかになることがあります。したがって、何でも特許を出せば良いというわけではなく、何をオープンにし何をクローズドにするかを戦略的に選択する必要があります。特許による独占期間が過ぎれば発明は誰でも実施可能になる点も踏まえ、ビジネスモデルによっては敢えて秘匿して継続的優位を図る方が賢明な場合もあります。
以上の課題から、ビジネスモデル特許は万能ではないことが分かります。特許を取得することで得られるメリットと、そこに至るハードルや維持のコスト・リスクを秤にかけ、総合的に判断することが重要です。特にサービス業ではスピード感が命ですから、特許出願すべきか否かの判断は事業戦略と整合させる必要があります。知財専門家の支援を受け、特許で保護すべき中核部分とそうでない部分を切り分ける作業も求められるでしょう。
まとめと今後の展望
ビジネスモデル特許はサービス業における知的財産保護の新たな柱として、その可能性と限界が見えてきました。技術とビジネスの融合が進む現代において、優れたサービスの仕組みを特許で保護することは、企業競争力の維持・強化に寄与します。一方で、特許制度の枠組みに乗せるための工夫や、権利取得後の運用に注意が必要である点も強調されます。
サービス産業の企業は、自社のビジネスモデルが特許に適しているかを見極め、適している場合は早期に出願して権利化を図るべきです。特許化が難しい部分については、他の知財手段(営業秘密としてノウハウを秘匿する、商標でブランドを守る等)や先行者利益による差別化戦略を検討することになります。今後、AIやIoTのさらなる発展により、これまで特許になじまなかったサービス領域でも特許取得のチャンスが生まれる可能性があります。例えば人的サービスの細かな提供プロセスも、AI支援やデジタルプラットフォームによって技術的側面が強化されれば、発明として成立し得るでしょう。
国や地域による制度差も踏まえつつ、ビジネスモデル特許を攻めと守りの知財戦略に組み込み、有効活用していくことが求められます。特に日本企業にとって、国内で得たビジネスモデル特許を海外でも権利化しグローバルに活用するアプローチや、逆に海外企業のビジネスモデル特許動向を注視して自社の立ち位置を考えることも重要でしょう。サービス業の知財戦略は製造業以上にダイナミックで、ビジネスモデル特許はその中核になり得る一方で絶対的な解ではありません。専門家はこのバランスを見極め、経営戦略と知財戦略の橋渡し役を担うことになります。
最後に、特許を含む知的財産の価値を最大化するには、取得した権利の適切な管理と活用が欠かせません。自社で活用しきれない特許であっても、他社にライセンスしたり売却したりすることで価値を生み出すことが可能です。そうした知財取引を促進するため、特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」(https://patent-revenue.iprich.jp)への無料登録をぜひご検討ください。知財のプロ同士が連携し、ビジネスモデル特許を含む知的財産を最大限に活用する時代が到来しています。サービス業における知財保護の実情を正しく理解し、ビジネスモデル特許というツールを賢明に使いこなすことで、知財立国時代の新たな価値創造につなげていきましょう。
(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
- 特許庁 審査第四部 審査調査室「ビジネス関連発明の最近の動向について」(2024年)〔https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html〕
- 大井一郎「ビジネスモデルで特許を取るには?概要と留意点を弁理士が解説」法律事務所ZeLo(2024年)〔https://zelojapan.com/lawsquare/46777〕
- 特許庁 審査第四部「ビジネス関連発明の権利取得について」(発明推進協会 知財実務オンライン説明会テキスト, 2021年)〔https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/document/chizai_setumeikai_jitsumu/26_text.pdf〕