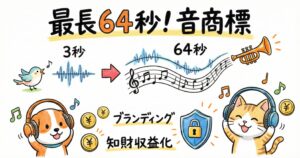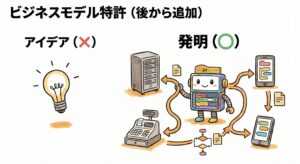マグアンプK事件に学ぶ商標権侵害のリスク:真正商品の小分け販売はなぜ違法となるのか

株式会社IPリッチのライセンス担当です。
本記事では、園芸用肥料として著名な「マグアンプK」を巡る商標権侵害訴訟(大阪地裁平成6年2月24日判決)を題材に、真正商品の「小分け販売」が法的にどのようなリスクを孕んでいるのかを徹底解説します。一般的に「正規ルートで購入した本物の商品であれば、それをどのように販売しようと自由である」と考えがちですが、知財法務の観点からは、そこに重大な落とし穴が存在します。本件は、登録商標が付された業務用の肥料を購入し、それを独自の袋に小分けして販売した行為が、商標の持つ「品質保証機能」を害するとして侵害認定されたリーディングケースです。企業や個人事業主が、善意であっても知財トラブルに巻き込まれることを防ぐため、この判決が示す法理と実務上の留意点を、専門的ながらも平易な言葉で紐解いていきます。
知財の収益化と専門人材の重要性
現代の企業経営において、知的財産権は単なる他社からの攻撃を防ぐための「防衛ツール」としてだけでなく、自社の利益を最大化するための「収益源」として捉え直す動きが急速に広まっています。「知財の収益化」というテーマは、保有する特許や商標をライセンスアウトしてロイヤリティを得ることに留まらず、他社の休眠知財を活用して新規事業を創出したり、ブランド価値を高めて商品の価格競争力を向上させたりといった、経営戦略の中核を担うものです。商標権一つをとっても、本記事で解説するように、正しく管理・活用しなければ収益どころか巨額の損害賠償リスクを抱えることになりますが、適切に運用すれば強力な独占排他権として市場優位性を確立できます。
このような高度な知財戦略を立案し、実行に移すためには、法律知識とビジネス感覚を兼ね備えた優秀な「知財人材」の確保が不可欠です。しかし、専門性の高い知財担当者を採用することは容易ではありません。そこで、もし貴社が即戦力となる知財人材の採用をご検討されているのであれば、ぜひ「PatentRevenue」をご活用ください。知財人材を採用したい事業者様に向けて、求人情報を無料で登録できるプラットフォームを提供しております。詳細はこちらのURL( https://patent-revenue.iprich.jp/recruite/ )からご確認いただけます。攻めと守りの両面から知財戦略を強化し、収益化を実現するための第一歩として、最適な人材との出会いをサポートいたします。
マグアンプK事件の概要と争点となった小分け行為
本事件は、園芸愛好家の間で広く知られる緩効性肥料「マグアンプK」を巡る商標権侵害訴訟です。原告である株式会社ハイポネックスジャパンは、登録商標「MAGAMP(マグアンプ)」を有し、同商標を付した肥料を製造販売していました。一方、被告となった株式会社草葉ナーセリーは、原告が販売する真正な業務用大袋入りの肥料を購入し、それを独自に小さな袋へと詰め替え(小分け)て販売していました。
被告は、小分けにした商品の販売場所に「マグアンプK」と記載した定価表を掲示し、さらに小分け後の商品パッケージや展示において「MAGAMP K」という標章を使用していました。ここで特筆すべきは、被告が販売していた肥料そのものは、紛れもなく原告が製造した「本物(真正品)」であったという点です。通常、商標権侵害といえば偽ブランド品やデッドコピー品の販売を想起しますが、本件では中身が真正品であるにもかかわらず、権利者から訴訟が提起されました。
原告は、被告による小分け販売行為が、原告の許諾なく商標を使用する行為であり、商標権の侵害に当たると主張しました。これに対し、本質的な争点となったのは、「真正商品を小分けして再包装し、元の商標を付す行為」が、商標法が保護する商標の機能を害するか否かという点です。被告側としては、「中身は原告の製品そのものであり、消費者を騙す意図はなく、むしろ大袋を必要としない消費者のニーズに応えている」という認識があったかもしれません。しかし、裁判所は商標権者の許諾なき加工・小分け行為に対して、非常に厳格な判断を下しました。この事件は、商標法における「使用」の定義や、真正商品の並行輸入とは区別される「加工・小分け」の違法性を明確にした事例として、現在でも実務上極めて重要な意味を持っています。
商標の品質保証機能と侵害認定のロジック
なぜ、中身が本物であるにもかかわらず、小分け販売が商標権侵害となるのでしょうか。その核心は、商標が持つ「品質保証機能」の保護にあります。大阪地方裁判所は平成6年2月24日の判決において、被告の行為を商標権侵害と認定しましたが、その理由は商標法の目的と機能に深く根ざしたものでした。
商標には主に「自他商品識別機能」(誰の商品かを見分ける機能)、「出所表示機能」(誰が作ったかを示す機能)、そして「品質保証機能」(一定の品質を備えていることを保証する機能)の3つの機能があると言われています。真正商品をそのまま転売する場合、商品はメーカーが出荷した状態のまま消費者に届くため、これら3つの機能はすべて維持されます。しかし、第三者がパッケージを開封し、別の容器に詰め替える「小分け」という作業が介在すると、事情は一変します。
裁判所は、小分け作業の過程において、肥料が湿気を帯びたり、成分が変質したり、あるいは異物が混入したりするリスクが否定できないと判断しました。たとえ小分け業者がどれほど注意深く作業を行ったとしても、商標権者(メーカー)の管理外で一度開封された以上、メーカーはその後の品質を保証することができません。もし、小分けの過程で劣化した商品を消費者が購入し、「マグアンプKの効果が弱い」と感じた場合、その不満は小分け業者ではなく、ブランドを表示しているメーカー(商標権者)へと向けられます。これにより、メーカーが長年築き上げてきたブランドへの信用(業務上の信用)が毀損されることになります。
判決では、現実に品質劣化が起きたかどうかに関わらず、品質の同一性が損なわれる「恐れ」がある状態で商標を使用すること自体が、品質保証機能を害し、ひいては需要者(消費者)の利益を害すると結論づけました。つまり、商標権の本質は単にマークを独占するだけでなく、「そのマークが付された商品が、権利者の管理下にある品質基準を満たしていること」を社会的に保証する点にあり、小分け行為はこの信頼の鎖を断ち切る行為であると見なされたのです。
損害賠償額の算定と推定規定の適用
商標権侵害が認定された場合、企業にとって次に大きな問題となるのが「損害賠償額」です。本件においても、行為の差止めと共に損害賠償が請求されました。商標権侵害における損害額の立証は、原告にとって容易ではありません。ブランドイメージの低下や、侵害品が売れたことで失われた売上(逸失利益)を正確に計算することは困難だからです。
そこで商標法第38条は、損害額の立証を容易にするための「推定規定」を設けています。
まず、商標法38条2項では、「侵害者がその侵害行為により受けた利益の額」を、そのまま商標権者の損害額と推定することができます。例えば、被告が小分け販売によって1,000万円の利益を上げていたとすれば、原告はその全額を損害として請求できる強力な規定です。これは、他人のブランドにただ乗り(フリーライド)して得た利益を吐き出させるという趣旨が含まれています。
また、商標法38条3項に基づき、「商標の使用料相当額(ライセンス料相当額)」を損害として請求することも可能です。仮に侵害者が「経費がかさんで利益は出ていない(赤字だ)」と主張したとしても、商標権者は「通常受け取るべきライセンス料」相当額を最低限の損害として請求できます。
マグアンプK事件の判決においては、裁判所は商標権侵害行為と相当因果関係にある損害額という観点から、損害の範囲を認定しました。解説によれば、当時の判決は損害の範囲を比較的制限的に解した部分もありましたが、侵害の事実自体は明確に認められています。近年の裁判例では、ブランド価値の毀損に対する無形損害や、弁護士費用相当額なども含めて賠償を認める傾向にあり、企業が負うリスクは増大しています。単に「小分けして売れば利益率が良い」という安易な動機で行ったビジネスが、結果として会社の屋台骨を揺るがす賠償請求につながる可能性があることを、経営者は強く認識すべきです。
加工や改変、商標の抹消における侵害判断
マグアンプK事件で示された法理は、単なる「小分け」にとどまらず、真正商品の「加工」や「改変」、さらには「商標の抹消」といった行為にも適用されます。
真正品を材料として加工し、新たな商品を製造販売する際に、元の商標をそのまま使用する行為も、原則として商標権侵害となります。例えば、有名ブランドの生地(真正品)を購入し、それを加工してバッグや小物を作成し、「〇〇ブランドの生地使用」として販売するケースです。これも商品の形状や品質が変更されており、元の商標権者が予定していない形態で流通することになるため、出所表示機能や品質保証機能を害すると判断されるのが一般的です。
さらに興味深い論点として、「商標の抹消」があります。登録商標が付された商品から、その商標を削り取ったり塗りつぶしたりして販売する行為です。「商標を使っていないのだから侵害にはならない」と思われがちですが、これについても侵害を肯定した裁判例が存在します。商標法は、商標権者が自社ブランドの商品を独占的に市場に流通させる権利を保護しており、商標を抹消して「どこの製品かわからない状態」で販売することは、商標が本来果たすべき出所表示機能を中途で抹消するものであり、権利者の利益を害すると解釈されることがあります。
このように、一度商標権者の手を離れた真正品であっても、それに何らかの手を加えて再流通させる行為は、知財法上非常にデリケートな問題を含んでいます。加工の度合いや商標の使用態様によっては、不正競争防止法違反(著名表示冒用行為など)に問われる可能性もあり、複合的な法的リスクを検討する必要があります。
真正商品の並行輸入との違い
ここで混同しやすいのが「真正商品の並行輸入」です。並行輸入とは、外国の真正な権利者から適法に販売された商品を、日本の正規代理店ルート以外のルート(第三者が外国で購入するなど)で輸入・販売する行為を指します。並行輸入に関しては、フレッドペリー事件などの最高裁判決を経て、一定の要件(当該商標が外国の商標権者により適法に付されたものであること、外国の商標権者と日本の商標権者が同一または法的・経済的に同視できる関係にあること、品質に実質的な差異がないこと)を満たせば、実質的違法性を欠くとして商標権侵害にはならないと解されています。
しかし、マグアンプK事件のような「小分け・加工」は、この並行輸入の免責要件である「品質に実質的な差異がないこと」を担保できない行為です。並行輸入が許容されるのは、あくまで「商品はそのままで、流通ルートが違うだけ」だからであり、商品の形状やパッケージを変更する行為が介在する小分け販売は、並行輸入の法理では救済されません。この区別を明確に理解しておかないと、「本物だから大丈夫」という誤った認識で違法行為を行ってしまうことになります。
事業者が徹底すべき実務対策とコンプライアンス
本件の教訓を踏まえ、事業者が商標権侵害を回避し、安全にビジネスを展開するために遵守すべき実務上のルールは以下の通りです。
第一に、「パッケージの開封・詰め替え・加工」を行う場合は、必ず商標権者の許諾を得ることです。もし業務用商品を小分けして販売したいのであれば、メーカーと正規のライセンス契約を結ぶか、あるいは「OEM供給」として自社ブランドで販売する契約を締結するのが筋です。無断でのリパッケージは、それがどれほど丁寧に行われたとしても、法的リスクを排除できません。
第二に、仕入れ商品の「状態」を常に確認することです。ECサイトやフリマアプリ等で商品を仕入れて転売する事業者の場合、仕入れた商品が既に第三者によって小分けされたものである可能性もあります。知らずに侵害品を販売してしまった場合でも、商標権侵害の責任(過失の推定)を問われる可能性があります。サプライチェーンの信頼性を確保し、正規の包装状態であるかを確認する検品体制が求められます。
第三に、自社商品が侵害された場合の対応フローを構築しておくことです。もし自社の商品が無断で小分け販売されているのを発見した場合、放置すれば低品質な商品が出回り、ブランド毀損のリスクがあります。速やかに弁理士や弁護士に相談し、警告書の送付やプラットフォームへの削除要請、場合によっては差止請求や損害賠償請求を行う断固とした姿勢が必要です。
最後に、新規事業や商品企画の段階で、必ず知財の専門家によるリーガルチェックを受けることです。「知財の収益化」を目指す上では、他社の権利を侵害しない「クリアランス調査」が前提となります。攻撃(収益化)と防御(コンプライアンス)は表裏一体であり、この両輪が機能して初めて、持続可能な知財経営が可能となります。マグアンプK事件は、商標という権利が持つ「品質への責任」の重さを、現代のビジネスに改めて問いかける重要なケーススタディと言えるでしょう。
(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献リスト
一般社団法人発明推進協会 判例要旨(平成6年2月24日 大阪地裁)
弁護士法人クラフトマン 非典型的な商標権侵害行為
石下特許事務所 真正商品の小分け販売と商標権侵害
石下特許事務所 損害賠償算定方法2~商標法第38条2項による算定
IPLaw-Net 商標権侵害 ブランド価値 毀損 損害賠償
Ankimaker 中途で抹消 商標権侵害
石下特許事務所 真正商品の並行輸入