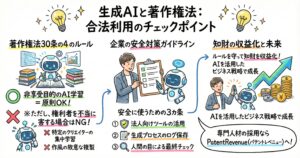スタートアップは大企業相手に通用する特許を取るべき!
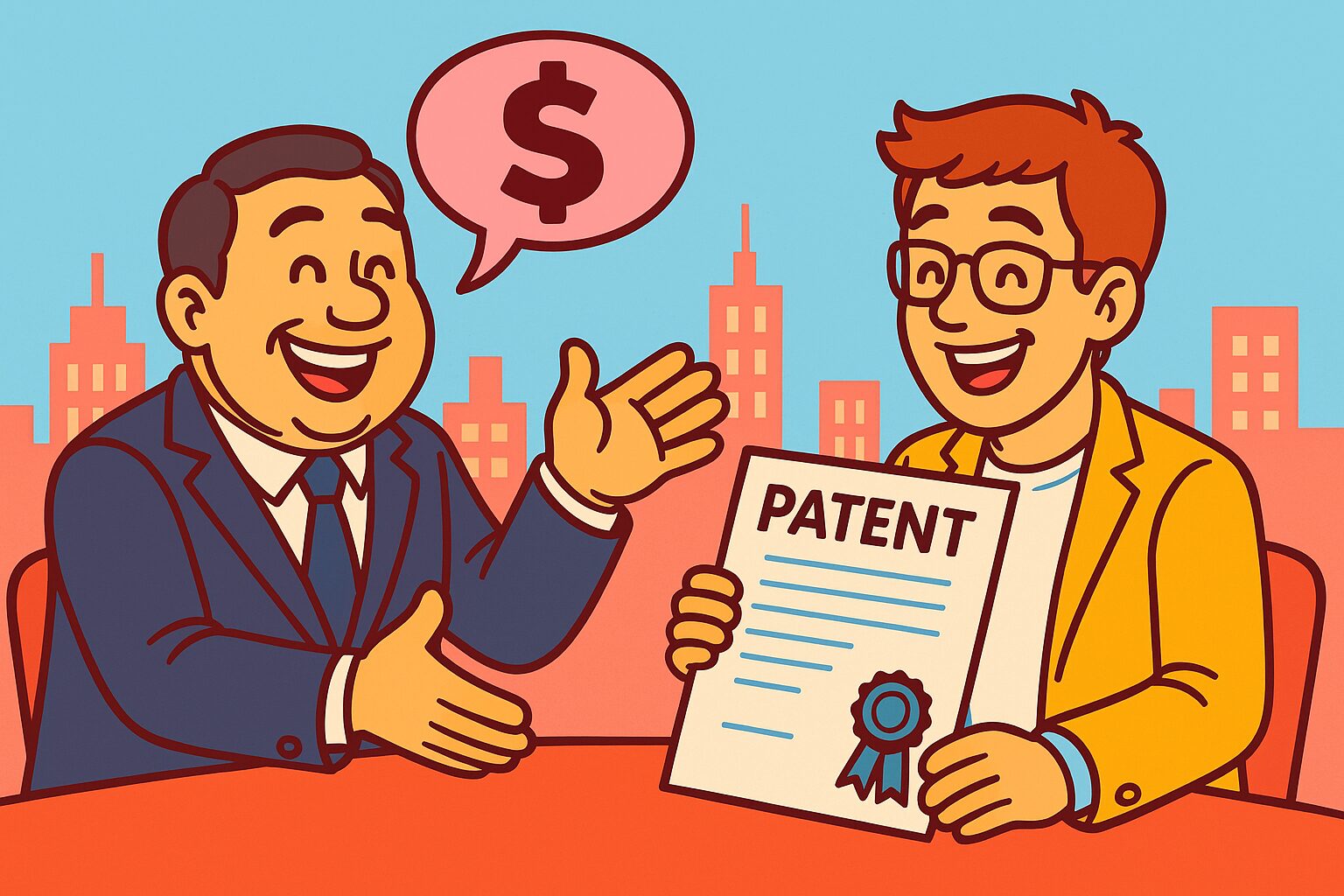
株式会社IPリッチのライセンス担当です。
スタートアップが大企業と戦うには、単なる技術力だけでなく特許の戦略的活用が必要です。本記事では、スタートアップが大企業相手でも通用する強力な特許を取得すべき理由とポイントを解説します。具体的には、回避できない特許、無効にならない特許、訴訟で勝てる特許、使いたがる特許の4つの視点から考察し、M&Aやオープンイノベーションにおける知財の役割についても説明します。
スタートアップと大企業:特許戦略の重要性
スタートアップにとって、巨額の資金や市場シェアを持つ大企業と戦うのは容易ではありません。革新的なサービスや技術を生み出しても、特許で保護していなければ大企業に模倣され、圧倒的な営業力で市場を奪われてしまうリスクがあります。逆に、特許権を取得しておけば、自社の発明を独占的に実施できるため、たとえ相手が大企業であっても無断でその技術を使うことは法的に許されません。特許権の存続期間(通常出願から20年)にわたり、競合他社の参入をブロックし、自社の競争優位性を守る強力な武器となります。
特許はまた、スタートアップの事業価値を高める重要な無形資産でもあります。経済産業省の調査によれば、米国ではエンジニアの能力や特許などの非財務情報が買収価額に反映されるケースが多いと報告されています[1]。ベンチャーキャピタルや事業会社からの出資・提携を引き出す際にも、「コア技術がきちんと特許で保護されているか」はチェックされるポイントです。実際、特許を取得済みの技術であること自体が、そのスタートアップの技術力や将来性を示す指標となり、企業価値評価において高く評価される場合があります。
さらに、特許の存在はスタートアップと大企業とのパワーバランスを変える可能性もあります。例えば、売上規模で自社の100倍ある大企業に対しても、たった1件の強力な特許があれば互角に渡り合えるとも言われます[4]。極端に聞こえるかもしれませんが、特許権は相手企業の製品生産や販売の差止めを求めることができる排他的権利です。もし大企業がスタートアップの特許を侵害すれば、その製品ライン全体の売上が止まるリスクが生じ、被る損害は計り知れません。一方、スタートアップ側の規模が小さい分、仮に訴訟になった際の被害額も限定的です。このように「攻めの知財」を確保しておけば、大企業も安易に無視できなくなり、場合によっては特許のライセンス交渉やM&Aの提案に持ち込むことも可能となるのです。
大企業が回避できない特許の構築
せっかく特許を取得しても、競合他社が少し設計を変えるだけで同じ機能を実現できてしまうようでは、その特許の価値は半減してしまいます。他社が容易に回避できるような権利では、特許を取得した意義が限定的になるとも指摘されています[3]。大企業は優秀なエンジニアを抱え、特許を迂回する「設計変更」を容易に行ってきます。スタートアップとしては、競合が迂回できない特許を目指して、権利範囲を慎重に設計する必要があります。
具体的には、発明の本質的なコアとなる原理やアルゴリズムまで含めて特許請求の範囲(クレーム)を定め、単なる実施形態の一例だけに留まらないようにする工夫が求められます。例えば、プロダクトのある機能を特許化する際、特定の構造や手法だけでなく、その機能を実現する基本原理にまで踏み込んでクレームを書くことで、競合が表面的な設計変更で特許を回避することを防げます。また、主要な技術要素それぞれについて複数の特許を取得し、網目のように守りを固める特許ポートフォリオ構築も有効です。こうした強力な特許網があれば、大企業側も容易な迂回ができず、その市場に参入するためにはライセンス交渉に応じざるを得なくなるでしょう。
さらに、自社技術を業界標準(スタンダード)に組み込んでしまう戦略も考えられます。標準規格に採用される技術についての特許、いわゆる標準必須特許(Standard Essential Patent)になれば、どんな大企業であってもその特許を回避してビジネスを行うことはできなくなります。実際、日本のある素材系スタートアップ企業では、自社でしか実現できない性能を業界基準にしようと試み、製造方法に関する特許を将来的な標準必須特許に位置づけることを意識して活動しています[5]。このように、技術の独自性を保ちつつ他社が迂回できない知財戦略をとることが、スタートアップには不可欠なのです。
無効にされない強力な特許を取得
どんなに有望そうな特許でも、他社から無効化されてしまっては意味がありません。特許庁で一度登録が認められても、特許には「異議申立て」や「無効審判」という制度があり、後から新たに発見された先行技術文献などに基づいて権利が取り消される可能性があります。また、特許権侵害で訴えられた被告は、しばしばその特許に無効理由があると主張して反論してきます。実際、日本の特許訴訟でも被告による特許無効の抗弁は頻繁に見られます[6]。このため、スタートアップがせっかく取得した特許を宝の持ち腐れにしないためには、無効になりにくい強い特許を最初から目指すことが重要です。
強い特許にするために押さえておきたいポイントをいくつか紹介します。
- 徹底した先行技術調査:出願前に国内外の既存技術(特許文献・論文など)を調査し、自社の発明が新規であることを確認します。他社特許と重複していないかを把握し、潜在的な無効理由を事前に洗い出します。
- 適切なクレーム設定:特許請求の範囲は広すぎても狭すぎても問題です。広すぎると既存技術に抵触して無効理由になりかねず、逆に狭すぎると権利範囲が限定されて回避されやすくなります。発明の本質を的確に捉えつつ、審査官とも議論しながら適切なクレームに調整しましょう。
- 明細書で裏付け:明細書(特許出願書類)の記載も重要です。発明の効果や具体的な実施例を十分に記載し、クレームを支える根拠を明確にしておきます。将来、無効審判で新規性・進歩性が争われる際にも、明細書の充実度が発明の説得力につながります。
- 継続出願や分割出願の活用:コア技術に関しては、一度の出願で終わりにせず、関連する改良や周辺技術について継続出願・分割出願を行うことも検討します。これにより、追加の特許でオールラウンドに守りを固めるとともに、一件が無効になっても他の特許でカバーできる体制を築けます。
このように質の高い特許権を確保しておけば、大企業から無効資料を突き付けられても簡単には崩れない強固な防壁となります。「特許を取った」こと自体に満足せず、取得した特許を盤石なものに鍛え上げる姿勢が、将来的な訴訟や交渉でもスタートアップを守る力になるのです。
訴訟で勝てる特許の条件
大企業を相手に特許権を行使して戦うとなれば、スタートアップにとっては大きな挑戦です。しかし「いざ訴訟になれば勝てるぞ」という切り札を手にしていることは、交渉上も極めて強力な武器となります。訴訟で勝てる特許とはどのようなものでしょうか。ポイントは、自社特許の権利範囲が競合製品・サービスに明確に及んでおり、侵害の事実を客観的に立証しやすいことです。
まず、特許請求の範囲(クレーム)の記載が曖昧ではなく、競合の製品がその構成要件を充足しているか一見して判断できることが理想です。権利範囲がぼんやりしていると、裁判になった際に解釈の余地を突かれて「自社製品は該当しない」と反論される可能性があります。反対に、クレームの記載が具体的で適切に広く、競合の製品仕様を明確にカバーしていれば、侵害の主張が認められやすくなります。
また、競合他社がその特許発明を使っていることの証拠をつかみやすいかどうかも重要です。例えば、製品の外観や仕様書から特許発明の使用が読み取れる場合は、証拠収集も比較的容易です。しかし、もし特許が生産工程や製品内部の構造に関するもので、外部からは確認困難な場合、侵害を立証するハードルが上がります。スタートアップの特許戦略としては、自社が権利を持つ技術が相手の製品で使われていることを示しやすい形で特許を取得しておくことが望ましいでしょう。
さらに、特許の執行力も勝敗を分けます。特許権者は裁判所に対して侵害製品の製造・販売差止めや損害賠償を請求できますが、強い特許であればあるほど差止め命令が認められる可能性が高まります。一件の特許侵害が認定されるだけで、大企業にとっては製品ライン全体が止まるリスクが生じます。そのため、大企業側は深刻な訴訟リスクを避けるために和解やライセンス契約に応じる動機が高くなります。実際に、日本でも素材特許1件で自動車メーカーの新型車生産が差し止め請求された事例があるなど、少数の特許でも訴訟に勝てるだけの威力を持ち得るのです[4]。
このように「訴訟で勝てる特許」を保有していることは、法廷闘争になった際の勝利可能性を高めるだけでなく、その前段階の交渉力として相手にプレッシャーを与える効果も絶大です。スタートアップとしては、万一の場合に備え、自社特許の侵害立証のシナリオを想定しておき、証拠収集の方法(製品分析や第三者機関による鑑定など)や専門の弁護士との連携体制を整えておくことも重要でしょう。
大企業が使いたがる特許とは
スタートアップにとって理想的なのは、「自社だけが使う特許」ではなく「他社も使いたがる特許」を持つことです。自社だけで市場を独占するのも一つの戦略ですが、場合によっては大企業でさえ「その特許技術を自社の製品に取り入れたい」と思うような魅力的な特許を持っていれば、スタートアップの存在感と交渉力は飛躍的に高まります。大企業から見て使いたい特許とは、言い換えれば価値の高い独自技術であり、性能やコストで代替がきかないものや、市場標準を左右するような技術です。例えば、新素材や画期的アルゴリズムなど、業界の課題を解決するブレイクスルー技術に関する特許がそれにあたります。
こうした「使いたがる特許」をスタートアップが保有していると、大企業はその技術を巡ってスタートアップとオープンイノベーションの関係を築こうとするでしょう。実際、あるスタートアップが多数の特許で強力な参入障壁を構築した結果、「その技術を一緒に事業化したい」という大企業からの協業オファーが相次いだケースも報告されています[5]。また、技術提携にとどまらず、大企業がスタートアップをまるごとM&Aで買収し特許ごと取り込んでしまう例も珍しくありません。それほどまでに、自社の成長戦略や製品ロードマップにとって重要な特許であれば、「ぜひ使わせてほしい」「自社のものにしたい」と大企業に思わせることができるのです。
スタートアップ側にとっても、自社の特許を他社にライセンスして収益化する道が開けます。独占的に事業展開するだけでなく、大企業とライセンス契約を結んで実施料収入を得ることで、自社の資金力を高めたり市場展開を加速させたりする戦略も可能です。その際、特許という明確な権利があることで、安心して技術提供・協業を行える土台ができ、ビジネス上のリスクも低減します。このように大企業が使いたがるような魅力的特許を持つことは、スタートアップにとって攻守両面で大きなメリットをもたらします。
特許がM&A・Exitの際に企業価値を高める理由
スタートアップにとっての最終目標の一つは、大企業による買収(M&A)や株式上場(IPO)などの形で投資回収(Exit)を実現することです。その際に特許を保有していることは、企業価値を押し上げる重要な要因となります。特許は単なる技術の証明ではなく、将来にわたり収益を生み出す可能性のある資産として評価されます。実際、海外では買収の際に対象会社が持つ特許ポートフォリオの価値がしっかり考慮され、買収価格に織り込まれるケースが多いとされます[1]。日本国内でも、近年はスタートアップの知財力が投資家や買収企業から注目されるようになってきました。
なぜ特許があるとM&Aで高く評価されるのでしょうか。第一に、買収する大企業の立場からすれば、スタートアップの技術が特許で保護されていることで、買収後にその技術を独占的に活用でき、他社に真似されるリスクを減らせるからです。特許のない技術だと、せっかく買収してもすぐに第三者に模倣されて競争優位を失う可能性があります。特許付きの技術であれば、少なくとも権利期間中は模倣品に対して法的措置を取れるため、安心して大型投資ができるのです。
第二に、特許はスタートアップの将来性を裏付ける指標でもあります。「この会社は独自技術を確立し、それを権利化する能力がある」という信頼感を与え、買収側もより高いシナジーを見込めます。特許庁の調査事例でも、あるスタートアップが事業拡大前に自社のコア技術をしっかり特許化していたことが評価され、ソフトバンクや大手証券会社から大型出資を受けたケースが紹介されています[5]。出資や買収の検討段階では、投資家や企業は「保有技術に特許が取られているか」を必ず確認すると言っても過言ではありません。それほど知財はスタートアップの価値評価に直結しているのです。
第三に、特許は投資回収のオプションを提供します。万が一スタートアップの事業が振るわなかった場合でも、保有する特許を他社に売却したりライセンスしたりすれば、一定のリターンを得られる可能性があります。投資家にとっては、最悪の場合でも特許資産が残ることで損失を抑えられるというリスクヘッジの意味合いもあります。特許売買の市場も徐々に整備が進んでおり、有望な特許は企業間で高値で取引されることもあります。
以上のような理由から、スタートアップにとって特許は単なる技術の証明にとどまらず、M&AやExit局面で大きな武器となります。自社の技術を磨くことと同じくらい、その技術を資産として保護・管理する知財戦略に力を入れることが、最終的な企業価値の向上につながるのです。
オープンイノベーションと知財戦略
近年、大企業とスタートアップが互いの強みを生かして新しい価値を共創するオープンイノベーションが盛んになっています。大企業の持つ資金や市場と、スタートアップの持つ革新的技術やアイデアを組み合わせることで、単独では成し得ないスピードでイノベーションを起こす狙いがあります。しかし、オープンイノベーションを成功させる上でカギとなるのが知的財産の取り扱いです。
共同開発や技術提携では、「どこまで情報を開示し、成果として得られた知見や技術の権利を誰が持つのか」という点を明確にしておかなければ、後々の紛争の火種になりかねません。そこで、あらかじめ秘密保持契約(NDA)を結んだ上で情報交換を行い、さらに共同研究契約やライセンス契約で知財の帰属や利用条件を定めることが重要です。特許を取得して自社技術の権利を確保しておけば、大企業とも対等に交渉しやすく、オープンにできる部分とクローズにすべきコアを切り分けた戦略も立てやすくなります。
政府・特許庁も、オープンイノベーション推進のために知財契約の整備を支援しています。例えば、典型的な連携パターンを想定した「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」が公開されており、契約実務のひな型や解説が提供されています。こうしたリソースも活用しながら、スタートアップ側としては自社の重要な知財を守りつつ、必要な部分はライセンス供与や共同出願など柔軟な対応を取ることで、大企業との協業を円滑に進めることができます。
オープンイノベーションにおける知財戦略は、攻めと守りのバランスが肝心です。自社のコア技術は特許などでしっかり保護した上で、大企業との間で知財の取り扱いに合意を取り付けることで、安心して技術を提供できます。一方で、相手企業から提供される技術やノウハウについても、自社との境界を曖昧にしないよう十分に注意を払い、契約書に明記しておく必要があります。知財のルールを明確にした協業は、双方にとってWin-Winの関係を築きやすく、結果としてオープンイノベーションによる新規事業創出の成功率を高めることにつながるでしょう。
大企業との情報共有時のリスクと対策
アイデアや技術を持つスタートアップにとって、大企業と情報共有・協業する際には知財流出のリスクに十分注意しなければなりません。善意で提携話を進めたつもりが、結果的に大企業だけに有利な形で技術を奪われてしまう例も現実に起きています。公正取引委員会の調査でも、下請け取引などの場面で「大企業にノウハウや知的財産を不当に吸い上げられた」と中小企業が感じた事例が多数報告されています[2]。具体的には、秘密保持契約がないまま詳細情報を伝えたところ、後になって大企業側がその技術を模倣した製品を独自に出したり、スタートアップに無断で関連特許を出願してしまったりするケースが問題視されています。
こうした事態を防ぐために、スタートアップが取るべき対策の例を挙げます。
- 秘密保持契約(NDA)の締結:初期段階から必ずNDAを取り交わし、提供する資料や会話内容に秘密情報である旨を明記します。NDAがあっても完全に悪用を防げるとは限りませんが、法的抑止力と証拠にはなります。
- 重要技術の先行出願:大企業と具体的な技術情報を共有する前に、可能な限りコア技術について特許出願(または仮出願)を済ませておきます。先に出願しておけば、後から相手が類似発明を出願してもこちらが先願権を主張できますし、技術内容を開示する際の安心感が違います。
- 情報開示のコントロール:提携交渉の段階に応じて、開示する情報の深さをコントロールします。最初から虎の子のノウハウまで全て渡すのではなく、相手の本気度や契約締結の進展を見極めつつ、開示範囲を段階的に広げます。「ここまで話したら契約する」という交渉上の区切りを設けることも有効です。
- 共有記録と証拠確保:いつ誰に何を開示したかを記録に残しておきます。メールのやり取りや配布資料には日付と版番号を付し、必要に応じて閲覧用資料には透かし(ウォーターマーク)を入れるなど、「自社提供の情報」であることを明示します。万一、後で相手が独自に開発したと主張しても、こちらが先に開示していた証拠を示せるようにしておくことが大切です。
以上の対策を講じても、100%リスクを排除できるわけではありませんが、少なくとも大企業側に「簡単には持ち逃げできない」と認識させる効果はあります。また、問題発生時に法的措置を取るための土台作りにもなります。スタートアップの技術は命綱ですから、自社の知財を守る意識を常に持ち、大企業との情報共有には慎重すぎるくらいでちょうど良いといえるでしょう。
大企業知財部の視点とスタートアップ
大企業には自社の知的財産を守り、他社の特許リスクを管理する専門部署(知財部)が存在します。彼らは日々膨大な特許情報をモニタリングし、自社の事業に影響を与える他社特許がないか目を光らせています。当然、有望なスタートアップが登場すれば、その企業がどれほどの特許を持っているか、将来自社にとって脅威になり得るかを綿密に分析します。言い換えれば、スタートアップの特許は大企業の知財部から評価され、値踏みされる存在なのです。
大企業の知財部員は、もしスタートアップの特許が自社にとって重要分野をカバーしていると判断すれば、以下のような選択肢を検討します。
- 回避策の模索:まずは自社でその特許を回避できるデザインアラウンドの可能性を検討します。技術的に少し迂回すれば特許侵害を避けられるなら、製品設計を変更する方向を提案するでしょう。
- 無効化の検討:その特許が自社にとって障害となりそうな場合、過去の文献を徹底的に調査し、無効理由がないか探します。大企業は調査のリソースも豊富なため、僅かな公開情報からでも無効資料を発掘してくる可能性があります。知財部としては、特許を潰せる見込みがあれば、無効審判を請求したり訴訟で無効主張する戦略を立てます。
- ライセンス・買収交渉:デザインアラウンドも難しく、特許の有効性も高いと判断すれば、知財部はビジネスサイドと連携してスタートアップとの交渉に動くでしょう。特許ライセンス契約を締結して使用許諾を得るか、いっそのこと会社ごと買収してしまうか、といった判断です。特許の重要度と相手企業の規模によりますが、経営判断として「お金を払ってでも権利を取り込むべきか」を検討します。
このように、大企業の知財部から見ると、スタートアップの特許は「無視できるか」「潰せるか」「それとも利用すべきか」を冷徹にジャッジされます。その視点に耐えうる質の高い特許を持っていることが、スタートアップが大企業と渡り合う上での信頼感につながります。一方で、知財部は特許の専門家集団であり、主張に無理があればすぐ見抜かれてしまいます。自社の特許ポートフォリオについては、自信を持てるエビデンスと論理武装を準備し、大企業との議論に臨むことが大切です。また、場合によっては知財部との技術的な対話を通じて相互理解が進み、協業や和解の糸口が見えることもあります。スタートアップ側も相手の知財担当者の考え方を理解し、適切な戦略とコミュニケーションを取ることが望ましいでしょう。
特許収益化戦略と「PatentRevenue」
スタートアップにとって、特許は防御や交渉の武器であると同時に、直接的な収益源にもなり得ます。自社では事業化しきれない技術や、保有しているが現在は使っていない特許があれば、他社にライセンスしてロイヤリティ収入を得ることができます。また、技術シフトやPivotなどで不要になった特許を売却すれば、一時金による資金調達も可能です。近年では、このような特許の売買・流通を支援するプラットフォームも登場しており、眠れる知財資産を有効活用する動きが広がっています。
特許の収益化を図る際には、どの特許に市場ニーズがあるか見極め、適切な相手とマッチングすることが重要です。ここで活用できるのが、特許売買・ライセンスのマッチングプラットフォーム「PatentRevenue」です。「PatentRevenue」は株式会社IPリッチが提供するオンラインサービスで、特許を売りたい企業と使いたい企業をつなぐマーケットプレイスとなっています。自社の特許情報を登録することで、興味を持った大企業や投資家から問い合わせやオファーを受けることができ、円滑な知財取引につながります。特許の評価額や適切なライセンシー候補が分からない場合でも、専門家の支援や各種データを活用して効果的なマッチングを支援してくれます。
特許の収益化は、スタートアップにとって新たなキャッシュ創出手段であるだけでなく、休眠特許が誰かの事業で活かされることでイノベーションの裾野が広がるという社会的意義もあります。自社の知財ポートフォリオを定期的に見直し、活用可能な資産は積極的に市場に出してみることも検討してはいかがでしょうか。その第一歩として、特許売買・ライセンスプラットフォームであるPatentRevenueにぜひご登録ください(https://patent-revenue.iprich.jp)。自社の眠れる特許が、新たな収益とチャンスを生み出すかもしれません。
(この記事はAIを用いて作成しています。)
参考文献
[1] 経済産業省『大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書』(令和3年3月)https://www.meti.go.jp/policy/economy/startup_kigyou/pdf/ma_survey2021.pdf
[2] 公正取引委員会『製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書』(2019年6月) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190612honbun.pdf
[3] 特許庁『戦略的な知的財産管理に向けて -技術経営力を高めるために- <知財戦略事例集>』(2007年4月) https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing_country/document/pdf/report_2007/02.pdf
[4] 植村 貴昭『特許の活用 中小企業が大企業に勝つには』(植村総合事務所コラム 第34回, 2019年9月27日)https://www.uemura-law.com/column/20190927/
[5] 特許庁『一歩先行く国内外ベンチャー企業の知財戦略事例集』(平成30年)https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing_country/document/pdf/report_2018/01.pdf
[6] 町野 静『第6回 特許無効の抗弁の主張・立証』(Business Lawyers, 2023年5月15日)https://business.bengo4.com/articles/949